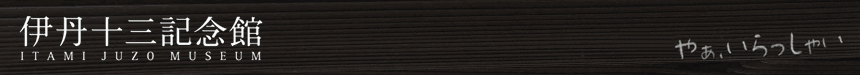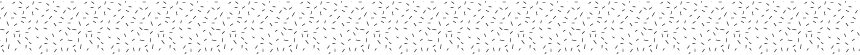こちらでは記念館の最新の情報や近況、そして学芸員やスタッフによる日々のちょっとした出来事など、あまり形を決めずに様々な事を掲載していきます。
2021.02.22 健康に痩せていよう
ダイエットに励んでいる知人がいます。
「隣町のショッピングセンターで買い物した後、家族が車で帰宅する中で自分だけ徒歩で帰ってきた」とか、「お酒は決めた量だけにしている」などという話を聞く度に、本当に偉いなあと感心します。
一方私はと言いますと、自分に甘くいろいろなことから目を背けて暮らしています。
最近の体重はわかりません。まず体重計が家にありません。
突然ですが、ここで問題です。
ふとりすぎの原因って何かご存知ですか?
正解はこちらです。
「ふとりすぎの原因は、十中八九、食べすぎであります。」
ートナリノケンチャンハドウシテアンナニフトッテルノ?-
『問いつめられたパパとママの本』より
先日、『問いつめられたパパとママの本』を読み返しておりましたら、目に飛び込んできました。
この直球すぎる伊丹さんの言葉が、深く刺さるのは何故でしょう。
ここでもう一つ、伊丹さんのエッセイの中で数年前に目にして以来、頭から離れない言葉がありますので、ご紹介いたします。
「肥った人はみんなそれまでに死んでしまうのです。痩せた人だけが生き残ってお年寄りになっているのです」
-食べものごときに過大な興味を持つな-
『ぼくの伯父さん』より
これは一体どういうことでしょう。この前後の文章も読んでみましょう。
八十とか九十とか、非常にお齢を召された方方、こういう方方は、まず例外なく、いわゆる鶴のように痩せておられるものです。
あれは一体どういうわけか?
「やっぱりあれよね、齢とっちゃうと、みんなあんなふうに痩せちゃうのよね」
なんていってる女の子がいる。とんでもない話であります。そういうふうに自分に都合のいいようにばかり世の中を考えるもんじゃない。いいですか、あれはだね、
「肥った人はみんなそれまでに死んでしまうのです。痩せた人だけが生き残ってお年寄りになっているのです」
そういうことなんだなあ。
どうも話が多少年寄じみてまいりますが、食べるということを真面目に考えるなら、どうしても健康ということを考えざるを得なくなる。
まず健康であること。特に二十六歳以後において健康であること。そのためには肥りすぎてはいけないよ。健康に痩せていよう。そうして、痩せているためには、食べるものに対する妄執をなんとか断ち切らねばならぬ。料理なんていうことを云々するのは、そういう大覚悟が為されてから後の話です。
-食べものごときに過大な興味を持つな-
『ぼくの伯父さん』より
ということです。
一見、厳しい話のようでいて、途中に出てくる「まず健康であること。」とか「肥りすぎてはいけないよ。健康に痩せていよう。」などという言葉は優しさが含まれていて、ホロっときますね。
という訳で、そろそろ私も伊丹さんの言葉を胸に「大覚悟を為して」、現実と向き合いたいと思います。まずは体重計を買ってきましょうか。
先ほどご紹介した『問いつめられたパパとママの本』のエッセイでは、あの直球の一文のあとに、痩せるために食事を改良する方法が詳しく語られています。今一度、心して読み直したいと思います。
ご紹介した2冊のエッセイはオンラインショップでも取り扱っております。
宜しければご覧下さい。
「ぼくの伯父さん」は こちら
「問いつめられたパパとママの本」は こちら
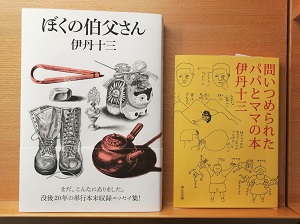
スタッフ:川又
2021.02.15 オトシモノの正体
秋から春先にかけての朝、外回りのお掃除をしておりますと、こんなものが落ちていることがあります。
駐車場の南西の角のところにバラバラと、ピスタチオみたいな質感で、大きさは枝豆一粒ぐらいのものが、多い時は......そうですね、30個以上。
初めて見たとき、すなわち、記念館に勤めはじめて間もない頃から「何かの木の実の種かな」「鳥の"オトシモノ"なんだろうな」「掃いても掃いても毎日これだけ落ちているのなら、たいそう美味しいのに違いない」と思ってはいたのですが、正体をつきとめられぬまま十数年――
恥ずかしながら最近やっと、たまたま手に取った鳥類図鑑でセンダンの種だと知りました。
センダンの実は、ムクドリやヒヨドリの好物なんだそうですね。(残念ながら、我々人間が食べると食中毒を起こして落命することもあるらしいです。)そういえば、それらしき鳥を庭や周辺でよく見かけます。
当然、センダンの木がこの辺りにあるということなのですが、名を知っているだけで姿は知らず、重ね重ねの恥ずかしながら、どんな木なのやら。
ぜひ見てみたく思っていましたら、これまた最近、記念館から2キロほど北の石手川緑地で発見しました。
「今日は鳥の声がにぎやかだな」「オヤ、あの木の下、何かの実がたくさん落ちてるぞ」とよくよく見ますと......
「これ、図鑑で見たヤツ!」
枝にも実がいっぱい。センダンの木っておっきいんですねぇ。
ここだけの話、月に3度は通るエリアなのに気づいてませんでした(笑)
と、記念館とあまり関係のないことを書き連ねてしまいましたが......旅行やお出かけに慎重にならざるを得ない今の状況、名所を訪ねて珍しいものを眺めたり食べたりするというような行楽的な体験はなかなかできませんけれど、遠出もできず人にも会えず、いつも同じところに身を置いて、同じことを繰り返す生活の中でこそ、ちょっとした出来事や変化に敏感に反応できたり、うまくすると長年の疑問が解けてちょっと嬉しかったり、そんなこともありますね、という一例でございました。
何度も読んだ本や見たことある映画の、いつもとは違うポイントで感銘を受ける、なんていうことも、もちろん大いにあるでしょう。
今はご来館の難しい方も、ぜひ本や映画で伊丹十三の世界に繰り返し触れていただいて、心身とも健やかにお過ごしいただきたいと願っています。(もちろんもちろん、ご来館も大歓迎です!)
どうか皆様、お元気に春をお迎えくださいますように。
学芸員:中野
2021.02.08 伊丹さんの猫の絵
記念館便りをご覧の皆さま、こんにちは。
まだまだ肌寒さを感じる日が続きますが、立春を迎え、記念館の近くを流れる川の土手では菜の花が咲き始めています。

さて、「猫好き」で知られる伊丹さんは、猫の絵をたくさん描いています。
鉛筆や筆で描いたもの、色をつけたもの...その絵をTシャツにプリントして家族や友人にプレゼントしたこともあったそうです。
一部の絵は記念館の常設展示室や、記念館のガイドブック等で紹介されていますので、ご覧になったことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。
 常設展示室「十 猫好き」のコーナー
常設展示室「十 猫好き」のコーナー
記念館のショップではそんな伊丹さんの猫の絵を使ったオリジナルグッズを販売しています。
猫好きで、かつイラストレーターとしても活躍した伊丹さんならではの猫の絵がプリントされたグッズは、伊丹さんと同じく猫好きの方はもちろんそうでない方にも「かわいい」「味わいがある」等などご好評をいただいているんですよ。お土産にもおすすめです!

猫3匹が並んだTシャツ
 ポストカード・缶バッジ・ゴム印
ポストカード・缶バッジ・ゴム印
ショップ店頭、また、オンラインショップでもお求めいただけますので、ご興味のある方はぜひごチェックしてみてください。
スタッフ:山岡
2021.02.01 伊丹十三記念館ホームページを覗いてみて下さい
明日は2月2日ですが、『節分』なんだそうですね。
2月2日の節分は明治30年以来、124年ぶりだそうです。
ちなみに伊丹十三の父親・伊丹万作が生まれたのは明治33年で、121年前のことです。
124年前を「伊丹万作が生まれる3年前」と言い換えると、よりわかりやすくなったでしょうか?そうでもないですか?
個人的にはぐっと身近に感じられます。
伊丹十三記念館には展示室やカフェなどに、伊丹十三だけでなく、伊丹万作に関する品々も展示していて伊丹万作によって描かれた絵画や書かれた日記を日々目にしているからでしょうか。
みなさまにもすぐにそれらをご覧頂きたいのですが、このご時世ですからご移動が難しい方もいらっしゃるかもしれませんので、本日は「ご自宅で」「今すぐに」伊丹万作を感じて頂く方法をご紹介します!
この伊丹十三記念館ホームページに、伊丹万作に関するページがあるのです、皆さまご存知でしたか?
伊丹十三の父、伊丹万作について書かれたページはこちらから⇒ こちら

写真も沢山、解説も詳しく大変読み応えがありますね。
その他、常設展や企画展のページなどもすごく充実しているのでお勧め致します。
また自由に動ける世の中になりましたら、その時には是非ともご来館の上で「ホームページで見た」ものの実物をご覧頂き、伊丹十三だけでなく伊丹万作の仕事や人となり、そして伊丹十三記念館を感じて頂けましたら幸いでございます。
それまで少しの時間、豆まきなどもしつつ、伊丹十三記念館のホームページの色々なページも覗いてみてください。
スタッフ:川又
記念館便り BACK NUMBER
- ●2024年10月
- ●2024年09月
- ●2024年08月
- ●2024年07月
- ●2024年06月
- ●2024年05月
- ●2024年04月
- ●2024年03月
- ●2024年02月
- ●2024年01月
- ●2023年の記事一覧
- ●2022年の記事一覧
- ●2021年の記事一覧
- ●2020年の記事一覧
- ●2019年の記事一覧
- ●2018年の記事一覧
- ●2017年の記事一覧
- ●2016年の記事一覧
- ●2015年の記事一覧
- ●2014年の記事一覧
- ●2013年の記事一覧
- ●2012年の記事一覧
- ●2011年の記事一覧
- ●2010年の記事一覧
- ●2009年の記事一覧
- ●2008年の記事一覧
- ●2007年の記事一覧