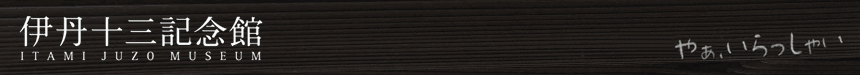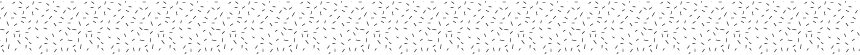こちらでは記念館の最新の情報や近況、そして学芸員やスタッフによる日々のちょっとした出来事など、あまり形を決めずに様々な事を掲載していきます。
2025.08.18 夏ニナルトドウシテ暑イノ?
毎日茹だるような暑さが続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
記念館では暑さに負けないよう、休憩を適宜はさみながら、日々水やりに取り組んでおります。そのおかげか、中庭の桂をはじめ、植物は元気に青々と茂っています。


昨年冬に松山市から引越しをして、通勤の際に電車を利用しているのですが、自宅から最寄駅まで歩く時間と、到着駅から記念館まで自転車を漕ぐ時間が、もう暑くて暑くて――始業前から尋常じゃない汗をかきつつ出勤しております。歩きの時間と自転車を漕ぐ時間はどちらも10分間に満たないのですが、これが意外にもしんどいもので、毎日体力を削られているのを感じます。
通勤を快適にするため、最近流行りのネッククーラーと呼ばれる、首に装着することで体温を下げるアイテムも試しましたが、自宅から最寄り駅までの徒歩10分でぬるくなってしまうため、記念館着くころにはただの首飾りになってしまいます。母曰く、「2500円くらいする良いやつを買ったらもちが全然違う」(私が持っているのはその半額以下のもの)とのことなのですが、「結局、大きめの保冷材が一番もつのでは?!」と思ってしまい、最近は保冷剤をタオルで包んでそのまま首にあてながら出勤しております。
さて、素朴な疑問ではありますが、夏というものはどうして暑いのか。こちらについては伊丹さんの『問いつめられたパパとママの本』の「夏ニナルトドウシテ暑イノ?」にて詳しく解説されておりますので、こちらをご覧ください。
夏が暑いのは、ひとつは日が長いせいであり、いまひとつは、太陽が真上から照りつけるせいであります。
じゃあ、日が長いと、どうして暑いのよ、なんていわないでおくれよ。同じ条件で物を熱するとするなら、十分間熱するより、十五分間熱するほうがよけい熱くなるだろうじゃないの。夏が暑い理由の第一は、だから、日が長いということであった。
では、次に真上から照らすと、なぜ暑いのか、というなら、たとえば懐中電燈を想像していただきたい。
懐中電燈の光を床に当てるとき、まっすぐ床に当てれば、小さいけれども強く明るい光の円ができるだろう。しかるに、それを斜めに当ててみようか。さっきより、ずっと床の近くから照らしても、照らす場所は広くなるかもしれぬが、明るさはずっと希薄になってしまうのが観察されるに違いないのであります。
つまりこの、垂直に照らすということなのだ、太陽がカンカン照るということは。
夏になると、太陽が真上から照らすから(その証拠に、夏の真昼の影は、小さく足元にまつわりついている)、したがって光や熱が強く当たり、冬になると、太陽が斜めに当たるから(その証拠に、冬の日は、真昼でも長く伸びている)、したがって地面を熱する力は弱くなる。
と、まあ、右のような二つの理由で夏は暑いわけだが、万全を期すためには、いま少し補わなければならぬことがある。
すなわち、もし右のような理由で夏が暑いとするなら、一番日が長く、かつ太陽が一番真上にから照らす夏至の日が、一年で一番暑くなければなるまいが、事実はそうではない。夏至の日は、梅雨の真最中で、曇や雨の日が多く、年によっては梅雨寒といわれるくらい涼しいこともあるのは皆さまご承知のとおりだが、これはなぜか。
別の例で説明しよう。同様なことが、一日のうちにも起こるのをあなたはご存じのはずである。
理屈からいうなら、一日のうちで一番暑いのは正午のはずであるはずだろう。太陽が一番真上から照らすのですから、太陽の光は正午が一番強い。
にもかかわらず、気温が一番高いのは二時ごろ、というように少しずれておりますね、これはなぜか。
地面というものは、太陽から熱をもらう一方、絶えず宇宙に向かって熱を発散しているわけですが、これを、収入と支払い、というふうに考えてみようか。
夜の間は日が照らないから、つまり収入はゼロであって、支払う一手。完全に冷えきったところで、サテ日が昇ったとしよう。
支払いは依然として多いが、収入は少しずつ確実に増えてゆき、ついに、収入が一致することになり(つまり、宇宙へ失う熱と、太陽からもらう熱が同じになり)、それからあとは、稼ぐに追いつく貧乏なし、収入が支払いを凌駕したのですから、貯金は増える一方だ。すなわち、どんどん、熱がたまってくる。
やがて、一番収入の多い正午を通りすぎ、これをピークとして収入は減り始めるが、しかし減り始めたとはいえ、いまだ依然として収入は支払いより多いから、貯金はまだまだ増える。ただ、その増えかたが次第に衰えてゆくわけですな。
そうして、ついに再び収入が下降して、支払いと一致する時期がやってまいります。貯金の額は、ここで最高に達するが、ここから先は収入が支払いを次第に下回って、つまり赤字がだんだん大きくなり、次の日の朝まで貯金で食いつながねばならん、ということになるわけですね。
つまり、一番収入が多い時期と、貯金が一番多い時期とは必ずしも一致するものではない、ということがおわかりいただけたかと思う。
収入が一番多かったのは、つまり日射が一番強かったのは正午であったが、貯金、すなわち、気温が最高になったのは、収入が下降して、支払いと一致する二時ごろであった。
こういうふうに収入と支払いのバランスによって、収入が最高の時と、貯金の額が最高の時とが少しずれる。
こういう現象が、つまり一日のうちでは、正午と二時、ということになって現れるし、一年の間では、夏至、つまり六月末と八月というふうになって現れることになるのであります。
ということが理屈ではわかっていても、まあ今日の暑さはどうだ。真夏の太陽が頭のてっぺんから、気の遠くなるほどガンガン照りつけて、ヘッ、あれが収入が次第に減りつつある姿かよ。われながら信じがたく思われる次第であった。
(『問いつめられたパパとママの本』より「夏ニナルトドウシテ暑イノ?」)
以上、夏になると暑くなる理由がお分かりいただけたことと思います。最近は最高気温が40度を越えるところもあり、大変暑さが厳しいですが、最後の伊丹さんのぼやきからも分かるように、エッセイが書かれた1960年代の夏も随分と厳しかったようですね。
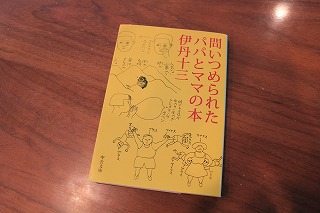
記念館にいて、特に暑さが厳しいと思う瞬間は、(水やりや草引きなど外での作業中はもちろんですが)真昼間の一番暑い時間帯に蝉が鳴かなくなるときです。
蝉が鳴く気温はおよそ25度~33度の間とされておりますため、34度以上になるともう鳴かないらしいのですね。最高気温が34度を越える日は、午前中は元気な蝉たちも、一日で一番暑い12時過ぎから14時ごろ、長いと15時ごろまではピタリと鳴かなくなります。それまでにぎやかだったのに、急に蝉の声が聞こえなくなるので「ああ、今日も34度を越えたのか...」と暑さが厳しいことを悟る日々です。
8月後半に入ったばかりでまだまだ暑い日が続きます。皆さまも熱中症にはくれぐれもお気をつけて、何卒ご自愛ください。
学芸員:橘