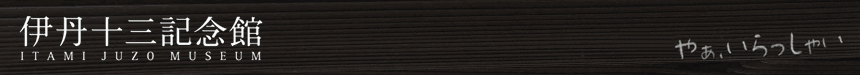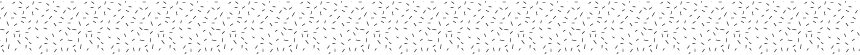こちらでは記念館の最新の情報や近況、そして学芸員やスタッフによる日々のちょっとした出来事など、あまり形を決めずに様々な事を掲載していきます。
2025.07.28 ラムネ
記念館便りをご覧の皆さま、こんにちは。
毎日毎日暑いですね。しかも、聞くところによると10月頃まで暑さが続くとか...。長期戦になりそうですので、水分・塩分をしっかり取って、お気をつけて毎日をお過ごしください。
記念館の中庭では、毎朝元気な蝉の大合唱が聞こえてきます。この時期、桂の木は蝉たちで大渋滞。幹や枝と同化していて分かり辛いのですが、よく見るとそこかしこに蝉がとまっていて、その数の多さに毎年びっくりします。
中庭の桂(と蝉)。
それぞれの写真に6~7匹ずつ写っています。
さて皆さまは、お祭りに行ったとき、立ち並ぶ屋台で「これはつい買ってしまう」というものはありますでしょうか。
焼きそば、たこ焼き、わたあめ、かき氷、焼きトウモロコシ、チョコバナナ、フランクフルトなどなど、食べ物だけでも書ききれない程たくさん売られていますし、それ以外では射的や金魚すくい、ヨーヨー釣り、お面などもありますね。
ちなみに私は小さい頃、かき氷とりんご飴が定番でした。いつもあれこれ迷うのですが、結局買うのはどちらかだったのを覚えています。
先日来館されたお客様は「お祭りの屋台ではラムネをつい買ってしまうんだよね」という方でした(ここでいうラムネは清涼飲料のことです)。
最近ですとプラスチック容器で売られているのもありますが、このお客様はビー玉が入った、いわゆる昔ながらの瓶のラムネを、お祭りの屋台で買うのが大好きなのだそうです。
そのきっかけが伊丹さんのエッセイだと仰っていましたので、内容を少しご紹介させていただきますね。
私が子供の頃聞いた話ではラムネの壜(びん)は「三田さん」という人によって発明されたものらしい。ラムネの壜は(今の若い人は知らぬだろうが)あれは実に子供心をそそるようにできていたね。
第一に蓋が表になくて壜の中に内蔵されているというアイディアが奇抜である。壜の首の中ほどにビー玉がはいっている。壜にラムネを詰めるとその炭酸ガスの圧力でビー玉は押し上げられて壜の口を内側から蓋してしまう。ビー玉というアイディアが憎いではないか。ついそこに見えているし、触ったりなどもできるのに決して取れない。これには参りますよ、子供は。
(中略)
ラムネはたいがい大きな、水を張った金盥の中に沈んでいたり、ブリキの箱の中に氷といっしょにはいっていて、だからラムネの壜は必ず濡れていた。乾いているあいだは口のところに検査証みたいな青い紙の封印がしてあるけど、冷しているうちにたいがい剝がれてしまう。
そういうラムネを買って、あの独特の「ラムネ蓋開け器」でもって、ラムネの蓋をシュポン!と抜く。ラムネが泡立って、ビー玉がコロコロして、うわあ、いいな。いいな。
「悪魔の発明」『女たちよ!』(新潮文庫)より
70代のお客様でしたが、小さい頃に飲んだラムネの記憶そのままが描写されていて、懐かしくて無性にラムネが飲みたくなったそうです。
「水を張った金盥の中で冷えているラムネを買って、瓶についた水滴をふき取りながら渡されて、シュポン!と開けて飲むのがいいんだよね!」ということで、そんなふうに売られているラムネを見かけるたび、エッセイを思い出して買うようになったとか。お祭りの屋台のほか、海水浴場もおすすめだそうですよ。
お客様と話をさせていただいたあとエッセイを読み返し、季節柄私も飲みたくなりました。お客様に倣い、お祭りに行ったときはラムネを探してみようと思っています。
夏にぴったりのエッセイですので、皆さまもよろしければ読んでみてください。おでかけ先でラムネを目にしたら飲みたくなるかもしれません。
スタッフ:山岡